別離の一言・迎えに来るぞ、親達は頼んだぞ・
夫婦の契りを結んで一週間にして、山田良政はその年の十一月上京。其の足でふたたび革命の暗雲乱れ飛ぶ支那に向けて旅立った。別れるときに、『向こうへ行って落ち着いたらきっと迎えに来るぞ。親達のことは頼んだそ』と言い置いて行った。それが永久の別離になろうとは知る由もなかった。
話は傍道に外れるが、明治三十二年と言えば、第一次広東革命に失敗した孫文が、日本にあって未来の秘策を練っていたときである。帰国以来、良政氏がたびたび上京したのも孫文達同士の者と画策するためだった。当時、良政氏は東京市神田区三崎町で梁山泊の様なものを設けていた。舎弟山田純三郎氏がはじめて孫中山の面影に拝したのも、やはり此所だった。
ある日、良政は集まっている青年達に、『今日だけは相撲を取らずに居れ。二時頃、支那の豪い人が来るから〜—』と言った。どんな豪い男が来るのかと思い、純三郎青年はじめ障子に指で穴を開けて覗いてみると額も後頭部も無闇に出っ張っている男の姿が見えた。その男こそ、中国革命の父と言われる孫文であった。
その後、上海で、広東で、孫文と山田良政はじめ日本人志士はしばしば画策した。そして、前に述べた恵州の旗上げとなった。義に勇む東亜の志士は、父母を、妻を故国に残し、上海の宿にある純三郎氏宛の『将来の日本に貢献するようにせよ』との書面をのこしたままついに恵州郊外三多祝の花と散ったのである。とは言え、乱世の常である、ましてや敗軍の跡は惨憺たるもので、山田良政氏の戦死は誰しも知らなかった。故郷に残る妻の敏子さんも、『志成ったらきっと迎えに来るぞ』の夫も一言を信じ、その日を待って義父母の許に仕えていた。その傍ら弘前女学校の教鞭をとった。明治三十三年から三十八年まで、官女は優しい良い先生として生徒達から慕われ、家庭にあっても實子も及ばぬ孝行をつくした。待てど暮らせど夫の消息は杳として分からぬが、基督教の強い信仰に培はれた忍耐心と、彼女の日本婦人としてのはげしい自覚は貧乏揺るぎもしなかった。今日、山田純三郎氏夫人は過ぎ去りし方をふりかえって、『姉さんはまったくお父さんやお母さんの面倒を見ていただくために、お嫁にきていたようなものですわ』と感慨深げに語ったが、敏子さんはその艱難を貫き通したのである。
明治三十八年、弘前女学校から母校の函館遺愛女学校へ転出し、明治四十年の函館大火には彼女の花嫁時代のかずかずの思い出の品を焼いてしまったけれども、夫を待つ貞節の心は巖の如く堅かった。郷当の近親者は彼女の崇高な気持に眼を瞠った。山田良政を知らぬ人達の間では、実の娘とすら思っていた。息子達を支那に送り、永い間便りもないまま老いゆく親の心は淋しかったにちがいない。父の浩藏氏はさすがに旧藩士であり、津軽塗の衰退を慨して同士と共に漆器授産の社を起し、うらぶれてゆく塗師群に更生の活力をあたえたほどの人物だけに、表にこそ弱味を見せなかったが、息子をおもう気持の切なさは嫁の敏子さんにも察しられた。が、敏子さんの蔭日向ない孝養に、老夫婦は淋しい気持を慰められた。山田浩藏氏は大正七年二月二十日、八十二才の高齢で歿した。流行性感冒が蔓延していた頃で、敏子さんは寝食を忘れて看護師した。
三多祝の土 ・貞烈報いられた慰霊祭・
南北に別れた夫山田良政を待って二十年。いつか帰る日があると彼女は待っていた。支那の黎明がくるのを待つ気持と、それは奇しくも結びついていた。その望みがようやく果たされたのは大正九年九月二十九日のことである。しかも、帰ってきたのは、いかにも革命志士にはふさわしく恵州郊外三多祝の土としてであった。
これよりさき孫文は、山田良政氏の功労を多として幕客朱執信を三多祝に遣わし、古老の聞き伝えによせて陣歿の地に遺骨を求めさせたが、その場所が判然しなかったので、已むを得ず四辺の土を拾って持ち帰り、日支の同志と共に東京でその土を祭って追悼会を催したのである。次いで孫文帷幕の要人廖仲愷は特使として、弘前貞昌寺に来たり、慰霊法要を行った。翌大正十一年の建碑除幕式には、孫文代理として幕客陳仲孚が弘前を訪れ、孫文は建碑記念詞を贈った。陳仲孚氏、汪主席特使として本年ふたたび弘前を訪れたのも、思えば奇しき因縁であった。陳特使は、弘前市主催の歓迎座談会の席上で感慨深く、『ヨーロッパは東洋において優越な態度を執っていました。その悪い政治をあらためさせるために起こったのが、孫文先生でした。支那はヨーロッパ、アメリカから追られている。亜細亜のための亜細亜を建設するという意志は、日本にも同士がありました。すなわち山田良政先生はその最も熱心な志士でした。中国革命は日本で一番』関係が深いのです。こんどこちらをまいり、山田先生の墓前に額づく機会を得たのはまことに欣快に堪えません』と語ったが、汪政権が大東亜共栄圏の一翼として力強い一歩を踏み出したいまこそ、敏子刀自の純潔荘厳な貞節は報いられたと言うべきだろう。弘前の旅館で、刀自は往時を回想してつぎのように語った。『小さい時から引込み思案で、思うことがあっても私には何と申してよいやら分からないのでございます。夫は豪胆な方でした。背丈は普通で、声も高い方ではありませんでしたが、いつもお友達と支那の問題の話に熱中していました。私はまだ若くて、何が何やら分からず過ごしましたが、あんな立派な方はないとそれのみ信じて生きてまいりました』琴瑟相和する折もなく、四十余年はしずかに、さびしく過ぎて行った。敏子刀自は本年六十六才。実家の藤田姓に戻った彼女は、彼女の姪に当たる人が住む芦屋市古屋敷二百十四番地、永井氏方に穏やかな余生を送っている。
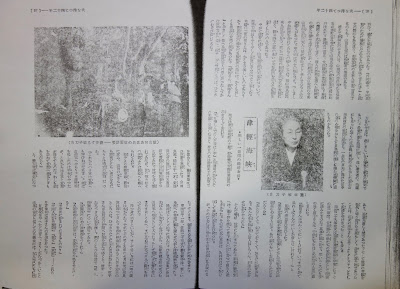
0 件のコメント:
コメントを投稿